今回は駐車と停車についてです。
みなさん、駐車と停車の違いってわかりますか?
おそらく長いのが駐車で、短いのが停車と思っている人が多いのでは?
今回は駐車と停車の意味についてです。(教本P270)
駐車
駐車は、車が継続的に(長くつづけて)停止することです。
例)
・客待ち、荷待ちによる停止。

このように、タクシーが利用するお客さんを待つためにロータリーに止まっている光景を見たことがあると思います。
一般の人でも待ち合わせた人が出てくるのを待っている行為も同じですので、
客待ち=人待ち
になります!
・5分をこえる荷物の積み下ろしのための停止
エンジンがかっていても又は、ハザードランプ(非常点滅灯)がついていても、5分をこえる荷物の積卸しのための停止であれば駐車になるということです。
さらに、運転者が運転席にいるいないに関係なく駐車ということになります!
・故障、その他 運転手が車から離れてすぐに運転できない状態での停止。
故障の状態も駐車として扱われます。
自分の意志でそこに止めている訳ではありませんが、道路上に障害物が存在しているので故障も駐車です!
あとは、
このように、コンビニの前に車を止めてちょっとした買い物に店内に入っていく行為も駐車です。
エンジンがかかっている、ハザードランプ(非常点滅灯)がついているは関係ありません!
正直なところ、「駐車」の定義の解釈の幅もかなり広いので、難しいところがあります。
なので、次のように明らかに「停車」となる場合を理解して、それ以外の停止が全て「駐車」になると思ったほうがいいでしょう!
停車
駐車以外の車の短時間の停止をいいます。
例)
・すぐに動ける状態の停止
道がわからなくなって地図を見るために止める。止まって人に道を尋ねるなど。
・人の乗り降り
人待ちの状態は駐車として扱いますが、送りに行ってその人を降ろしてすぐに発進できる状態であれば停車になります。
人の乗り降りについては、時間制限はありません。
(車いすの人の乗降で時間がかかることも現にあります。待機状態は「待ち」になるので含まれません)
・5分以内の荷物の積み下ろしのための停止
集配行為(郵便、新聞などの配達)は含まれていません。
ただし、伝票の受け渡しや荷物を運ぶときは近い距離でなければなりません。
・法令の規定による一時停止など
「止まれ 」や信号
」や信号 による停止や危険を防ぐための停止などのことです。
による停止や危険を防ぐための停止などのことです。
まとめです。
1、運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態であれば、1分でも駐車ということになる。
2、人の乗り降りは、時間制限はなく「停車」である。(人待ちは駐車)
3、5分という時間が関係しているのは「荷物の積み下ろし」だけである。
おさらい問題(答えは一番下↓)
1、友人を待ってすぐに運転できる状態であれば、5分以内は駐車にならない。
2、車が故障したときは、駐車禁止場所であっても車を止めることができる。
3、乗降時に5分をこえてしまったが、人の乗り降りのための停止なので、駐車にはならない。
(裕)でした。('-^*)/
よかったら押してください↓
こちらもよろしくです↓
1、×(人待ちの行為は「駐車」です。)
2、×(故障した場合も継続的な停止になるので「駐車」になります)
3、○(人の乗り降りという行為は時間に関係なく「停車」になります)
















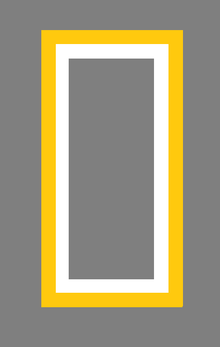


























































 の標識が出ている道路では、はみ出さなければ追い越しをしてもよい。
の標識が出ている道路では、はみ出さなければ追い越しをしてもよい。






































